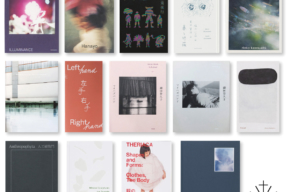写真家×編集者トーク: 解放と再生へ向かう物語―古賀絵里子『BELL』

道成寺に伝わる悲恋の伝説「安珍・清姫物語」を下敷きに、写真集『BELL』を発表した古賀絵里子さん。
今日的な視点と写真という形式による再話は、全編が驚異の感覚に満ちあふれ、古賀さんにとって新たな境地を切り開く作品となりました。
版元である赤々舎の姫野希美さんも加わり、制作の裏側を語っていただきました。
*本記事は2021年5月に発行した「LAB express vol.03」から転載しました。

古賀絵里子写真集『BELL』より
なぜ古典をモチーフにしたのか
── 新作ではモチーフとして「安珍・清姫物語」が用いられています。この物語は、僧の安珍に裏切られた清姫が、怒りのあまり蛇に変化し、鐘ごと安珍を焼き殺すという内容で、能楽や人形浄瑠璃、歌舞伎など、さまざまなかたちで演じられてきました。日本でもっとも有名な悲恋の伝説を、制作の枠組みにつかった理由は何だったのでしょうか。
古賀: はじめてこの物語を知ったのは20代の頃。川本喜八郎さんの人形アニメーション「道成寺」で、清姫の強い思いと悲しみの表現が印象に残っていました。そして、8年前に結婚した相手が妙満寺の塔頭の住職だったんですね。じつは妙満寺には「安珍・清姫の鐘」が納められているんです。それで、ますます「安珍・清姫物語」を身近に感じるようになって、わたしなりに、いつか写真で表現したいと思うようになったという経緯があります。そんななか、姫野さんをとおして、ニコン イメージング ジャパンの方から企画展のお話をいただきました。
姫野: お話があったのは2018年。2020年にニコンプラザ東京と大阪で、新作の展示をおこなってほしいというものでした。
古賀: このとき覚悟を決めました。長年温めてきた「安珍・清姫物語」をテーマにするしかないと思ったんです。とはいうものの、写真で表現するにはどうしたらいいのか、まったく見当がつかなくて、けっこう悩みましたね。生半可な気持ちでは手をつけられない。そういう思いがあったものですから……。姫野さんがアドバイスをくれたんですよね。たしかコレオグラファーの話をしてくださった。
姫野: 参考になるかなと思って、一例として、ピナ・バウシュのことを話したんです。ヴッパタール舞踊団を率いていた振付家・舞踊家で、ダンスと演劇を融合させた舞台で知られています。彼女が振付を考えるときは、個々のダンサーたちの出自や背景をふまえながら、身体の動きを構成していく。おなじように、古賀さんが「安珍・清姫物語」に向きあうとしたら、あらすじをそのままなぞるのではなく、古賀さんのまわりには魅力的な人たちがたくさんいるのだから、周囲の方々に協力してもらいながら、物語のなかにあるさまざまな「場面」を演出していけばいいんじゃないか。そんなことを喋りました。

古賀絵里子写真集『BELL』より
写真ならではの表現を求めて
古賀: そこから制作の糸口が広がっていった感じです。夫を含めたお坊さんが安珍を、自分や友達が清姫を演じることにして、場面ごとの演出を考えていきました。「ふつうの人たち」が演じることで、物語が普遍的なものになると思ったんですね。と同時に「安珍・清姫物語」を女性の立場から見直したいという意図もありました。一般的なイメージでいうと、清姫は執念深い女ととらえられていますが、自分が清姫の立場になったとしたら、彼女の行動にはものすごく共感できる。恋愛中は誰にだってそういう側面はありますから。安珍だって清姫と一夜を共にするわけですから、けっして清廉潔白な人物だったわけではない。わたしのまわりにいるお坊さんたちも、祇園に飲みにいくような俗っぽさを持ちあわせていますし(笑)。
── これまでの写真集が「目の前の情景を自然な光で撮影する」というトーンだったとすると、今回はストロボを使用したり、ブレ・ボケ写真を採用したり、いままでのやり方から大きく踏み出していますね。物語の解釈含め、写真そのものに自由な感覚がみなぎっている印象を受けました。
古賀: 2歳の娘を育てながらの撮影で、日々の暮らしのなか、制作のための時間をつくること自体が、もうほんとうに大変で。そのうえ、作品にかんしても「はたして、こんな写真でいいんだろうか」と自問自答のくりかえしでしたから。試行錯誤で悩みながらも、撮影を続けていたら、あるとき娘が描いた絵に衝撃を受けた。チューブからいきなり絵の具を手のひらに出して、真っ白い画用紙にぶわっとぶちまけた(笑)。でも、それが目もさめるような色の組み合わせになっていたり、考えもつかないような形になっていたりしていて、なんとのびやかなことかと心底驚きました。ああ、表現ってもっと自由で楽しいものなんだよなと再認識したんです。そのあとは今まで作品ではあまりやってこなかった撮影方法を、どんどん試してみるようにしました。フラッシュをたいたり、赤外線フィルターをつかったり、水中カメラにチャレンジしたり、超望遠レンズで月のクレーターを撮ってみたり……。
姫野: ストロボをつかった写真は印象的でしたね。安珍と清姫の道行きを生々しくとらえているように感じられて。これまでの古賀さんの写真とはまったく違っていて、とても大胆だと思ったし、なにより新鮮でした。古賀さんは場面のなかに宿っている動きをとらえようとしていますが、これまでの安定したやり方を捨てて、新しい方法論をとりこむというのは、そこに表現者としての切実さがあるのだろうとも思います。
古賀: 「安定を捨てる」というのは、たしかにそうですね。制約も多かったけれど、表現の幅は広がったと思います。

古賀絵里子写真集『BELL』より
明るい光にあふれた世界へ
── 悲恋の物語と考えられてきた「安珍・清姫物語」の筋立てを、『BELL』は心地よく裏切ってくれます。終盤に向かうにつれ、静かに浄化されていく気分になりました。
古賀: 2018年から2019年にかけて、おおよそ1年間、集中的に撮影をしてきました。2020年に入ってから、全体の流れを組みはじめたのですが、写真の選び方や並べ方をていねいに考えていかないと、予定調和めいたもので終わってしまいます。いままでにない表現をめざしていたので、それだけは避けたかった。撮影とおなじく、このときも試行錯誤の連続でした。
姫野: 最初の案をいったん見せてもらってから、写真を差し替えてみたり、構成を組み直したりしました。構成にかんしては、3回くらい根本的に大きくやり変えたんじゃないか。
古賀: それでも最後の写真がどうしても決まらない。本の流れがうまく落ち着かないというか、どの写真を入れてもしっくりこない。姫野さんからも「絵里子ちゃん、いままで撮ってきた写真のなかにはないかも」と言われて、正直ちょっと落ち込みましたね。もう一回、深い撮影の海に潜るのかと(笑)。
姫野: 女性が負わされた痛みを踏まえたうえで、でも、何か未来を感じさせるようなもの。そんな写真があればいいなと思ったんですよね。
古賀: 自分の作品なのに、最後に収めるべきものが、そのときのわたしには見えていなかったんです。それまでも、どう撮っていいのかわからなくなったら、物語に立ちもどるということをしてきたので、もういちど「安珍・清姫物語」を読んでみました。鐘のなかで安珍が焼き殺され、清姫が入水したあと、蛇道に落ちたふたりは法華経の功徳で成仏します。そして、ふたりは天人となり天上界へ舞い上がるという場面で終わります。わたしにとって、そこは明るい光にあふれた世界に感じられました。と同時に、そういう光景を撮影すればいいのだとも気づいた。それで夏の朝、満開の蓮の花の前で、光につつまれた娘を撮りました。演出はせず、日常生活のなかのひとこまとして。
姫野: あの写真はまさに「これだ!」という感じでしたね。最後のピースがきちんと嵌め込まれた。
古賀: 自分にとって光にあふれた世界とは何かを考えたとき、それは娘が存在することだった。子供は光であり、希望です。結果的に「安珍・清姫物語」をとおして、過去や家族を見つめなおすことにつながり、そこから未来も見えてきたように感じています。苦労も多かったけれど、皆に支えられながら撮影と制作をつづけることで、自分自身、解放されました。「誰もが安珍であり、誰もが清姫である」という思いを、常にいだきながら制作した作品です。『BELL』を手にとってくださる方々も、この作品を通して、自分自身の物語をたどっていただけたらうれしいです。

左:古賀絵里子写真集『BELL』, 右:弊社印刷現場での立会の様子(右:古賀絵里子さん、左:赤々舎・姫野希美さん)
古賀絵里子『BELL』
160ページ、220×250mm 6,000円+税
発行日|2020年11月 発行|株式会社赤々舎
造本設計・デザイン|大西正一 印刷・製本|ライブアートブックス
*本書のご購入は赤々舎のウェブサイトをご覧ください。
「LAB express vol.03」について

本記事は2021年5月に発行した「LAB epress vol.03」から転載しました。
「LAB express vol.02」についての詳細はこちら→ よりご覧ください。